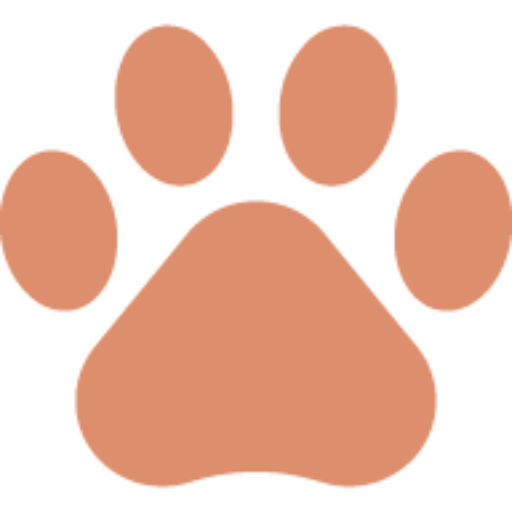- もしもの時
2023.03.16
もしも迷子になったら

この記事の目次
猫用の柵をつけていたり、玄関とつながる扉を閉めていたり、対策しているつもりでも、突然猫が外に出てしまうケースがあります。
室内飼いの猫が多いこともあり、外は見知らぬ世界。
突然のできごとに、普段とは違う行動に出る猫もいます。
猫が迷子になってしまったら、飼い主さんの対処が重要です。
できるだけ冷静に、できるだけ速やかに、取るべき行動を実践しましょう。
猫が迷子になってしまった時の行動5つ
自宅の近くをよく探す

猫は知らない場所を怖がるケースがほとんどです。
そのため、どうしたら良いのか分からず、近所でじっとしている場合が多いでしょう。
まずは自宅近くや物陰を、くまなく探してみてください。
飼い猫の名前を呼ぶ場合は、できるだけ優しく、普段通りの声かけが大切です。
焦って大声で呼んでしまうと余計に怯えてしまうため、注意しましょう。
探す際には、大きめの洗濯ネットを持っておくと便利です。
猫を見つけたら、逃げられないように洗濯ネットをさっとかぶせ、キャリーケースに入れて連れ帰りましょう。
迷子チラシを作成する
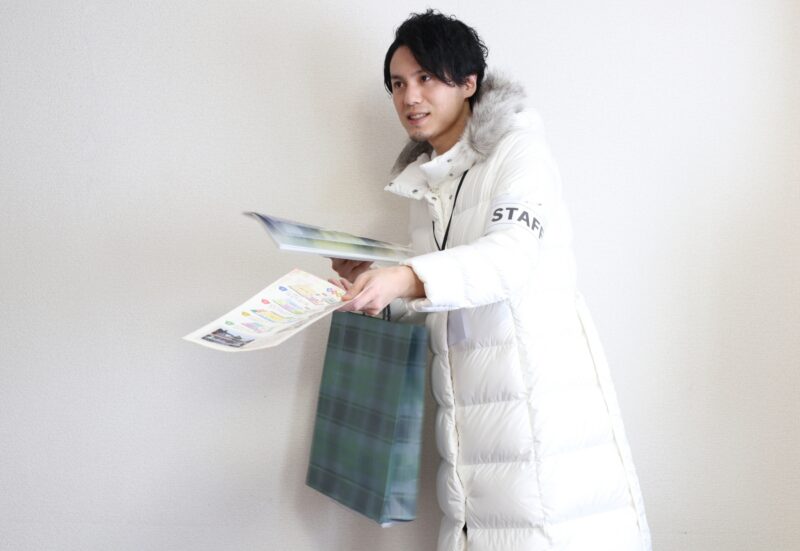
猫の目撃情報を集めたり、保護している人に飼い主さんの情報を伝えたりするために、迷子チラシが欠かせません。
大阪市など、迷子チラシのテンプレートを無料で配布しているサイトが多数あります。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000471139.html
チラシ作りに時間をかけないためにも、情報を当てはめるだけで完成できる、テンプレート活用がおすすめです。
チラシが完成したら、自宅近くに貼り出したり、近所のお店やコンビニなどに置かせてもらったりして、情報提供を待ちましょう。
警察や動物病院などに連絡する

保護された猫が届けられていないか、警察や近隣の動物病院、動物愛護センター、保護猫団体などに問い合わせてみましょう。
この時、迷子チラシを持って直接足を運ぶと、猫の写真や特徴を分かりやすく伝えられます。
動物病院や保護猫団体によっては、チラシを置かせてもらえる、貼り出してもらえる場合もあります。
訪問した際に、お願いできないか聞いてみましょう。
SNSで情報を拡散してもらう

迷子猫の情報が、TwitterやInstagramなどで日々発信されています。
「#拡散希望」のハッシュタグをつけておくと、猫好きなユーザーの善意で、情報を広めてもらえるでしょう。
SNSやブログなど、メディアを通じて情報発信する際も、チラシデータが役に立ちます。
手書きで迷子チラシを作る場合は、チラシを撮影の上、Webへ掲載しましょう。
保護猫情報サイトをチェックする

環境省や全国の自治体など、さまざまなサイトで保護猫情報が掲載されています。
「環境省/収容動物検索サイト」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/
猫が迷子になってしまったら、情報が出ていないか、地域のサイトを確認してみましょう。
首輪やマイクロチップで見つかることも

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーを通じて販売する猫の、マイクロチップ装着が義務化されました。
マイクロチップには、飼い主さんの情報が登録されています。
誰かが猫を保護してくれた場合、マイクロチップの情報をもとに、飼い主さんと出会える可能性があります。
マイクロチップを装着していない猫も、飼い主さんの情報を首輪に書いておくと、保護された際に役立つでしょう。
成猫になってからでは首輪を嫌がるケースが多いため、子猫のうちから慣らしておくと安心です。
最近は、GPS機能がついた猫用首輪も販売されています。
脱走歴が多い猫の場合は、GPS機能の付いた首輪をつけておくと、すぐに位置を確認でき便利です。
サイズや重さがさまざまなため、猫が嫌がらないかどうか、負担にならないかどうか検討の上、購入するかどうか決定しましょう。
まとめ
大切な猫がいなくなってしまった時、動揺してしまう飼い主さんがほとんどです。
不安な場面ですが、愛猫のためにも速やかに行動を起こしましょう。
対処が早ければ早いほど、見つかる可能性が高くなります。
できる行動はすべて取り入れて、一刻も早い再会を目指しましょう。
- もしもの時