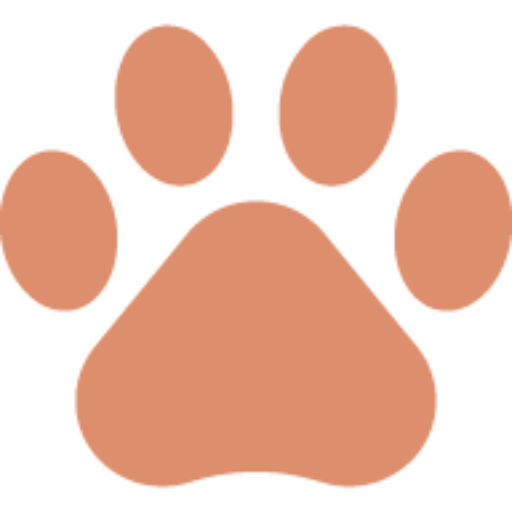- 猫と暮らす
- ピックアップ
2023.03.16
1歳になるまでの成長過程と飼育で大切なこと

100gくらいで生まれる仔猫。
てのひらに乗るくらい小さかった仔猫も、半年を過ぎる頃には成猫と変わらない3~5kgくらいに成長します。
猫は、生後1年で人間の18歳くらいに育つといわれ、とくに慎重に飼育するべき期間です。
1歳になるまで猫はどのように成長するのか。
育てる中で、どのような点に注意するべきか。
飼育の基本をチェックしておきましょう。
1歳までにするべきこと

1歳になるまでに、かならず済ませておきたいのが
「ワクチン」「去勢・避妊手術」「ノミダニ予防」「必要に応じた駆虫」です。
適したタイミングや注意点をみてみましょう。
猫用ワクチン接種
1歳までの仔猫は、年に2~3回のワクチン接種が必要です。
選ぶべきワクチンの種類や接種の間隔は、仔猫が育ってきた環境や月齢によって違います。
基本的には8週齢で1回目のワクチン接種。その後、約4週間の間隔で2~3回追加接種します。
最終ワクチンは生後16週くらいに打つのがベストです。
ワクチンプログラムは、かかりつけの獣医師に相談してください。
生後半年を過ぎた猫を拾ったなど、迎える時期によってワクチンを打つタイミングが変わるため、早めに獣医師へ相談しましょう。
ノミダニ予防
外に出る猫は、1年を通じてノミダニ予防が必要です。
完全室内飼いでも、突然脱走してしまったり、飼い主さんの服にノミがついていて持ち帰ってしまったり、というケースがあります。
災害などで、突然外へ連れていくケースを考えるのであれば、ノミダニ予防を済ませておきましょう。
外で拾った猫の場合、はじめからノミがついているケースが多くあります。
この場合は、動物病院で駆除薬を処方してもらいましょう。
ノミダニの予防薬は、使用する薬によって使える週齢が決まっています。
獣医師と相談の上、適した駆除薬、予防薬を選択してください。
去勢・避妊手術
去勢・避妊手術は生後6か月くらいが目安です。
仔猫を望まない場合は、発情期を迎える前に手術を検討しましょう。
発情期を迎えてしまうと、外に出たいという欲求が高まり、室内飼いがストレスになってしまいます。
オスの場合は、スプレー行為で部屋が汚れてしまう恐れもあるため、早めの手術がおすすめです。
雌の場合は、乳がんの発生がホルモンバランスに関係していると分かっています。
具体的には、1歳までの避妊手術が乳がんの発生率を86%低下すると報告されています。
避妊手術で卵巣や子宮を取り除いていれば、卵巣がん、子宮蓄膿症などの病気を心配しなくて良い、という点もメリットです。
去勢・避妊手術は、ワクチンやノミダニ駆除が終わっていないと手術が受けられない病院がほとんどです。
フィラリアやお腹の虫の駆除・予防が条件になっている動物病院もあります。
生後6ヶ月頃に去勢・避妊手術を受けられるように、ワクチン接種やノミダニ駆除のタイミングを動物病院で相談しましょう。
1歳までの食事の変化

生後間もない猫を迎えた場合、生後1か月くらいまでは猫用ミルクで育てます。
1ヶ月を過ぎるころには歯が生えそろうため、お湯でふやかした仔猫用のドライフードを少しずつ与えましょう。
1ヶ月以降はミルクだけでなく、お水を浅いお皿に用意してあげてください。
生後3~4ヶ月頃には、ふやかしていないドライフードを食べられるようになります。
生後半年~1年くらいまでは、仔猫用のフードを選んでください。
生後半年~1歳になったからといって、いきなり大人用のフードに変えてしまうと、お腹をこわしてしまう場合があります。
また、生後半年くらいで去勢・避妊手術を受ける猫が多いこと。
最近は、避妊去勢後用のフードが販売されていることから、これらのフードを活用するのも良い方法です。
去勢・避妊手術をしたからと、すぐフードを変更してしまう飼い主さんがみられますが、まずは体調の安定が最優先です。
体調が落ち着いたら、仔猫用フードに少しずつ大人用フードを混ぜて、少しずつ切り替えましょう。
年齢に適したしつけスタート

猫を迎えたら、週齢に適したしつけをしましょう。
しつけ、といっても猫を叱るのはNGです。
この時期に怖い体験をすると、一生トラウマになってしまう場合があります。
問題行動がある場合も、叱るのではなく、いたずらできないように環境を整えましょう。
生後2週~8週くらいの猫は社会化期と呼ばれ、社会行動を学ぶ時期です。
この時期にブラッシングや爪切り、歯みがき、キャリーバッグ、ケージなどに慣らしておくと、習慣化できます。
他の猫、動物とのかかわりあいにも深く影響を与える時期です。
人なつっこい猫にしたい場合は、ストレスにならない範囲で、いろいろな人に撫でてもらいましょう。
社会化期は、免疫力が低い時期でもあります。風邪をひいている猫、過去に風邪をひいたことがある猫、
猫白血病ウイルスや猫エイズウイルスなどに感染している猫、検査をしていない猫との接触は避けてください。
社会化期を過ぎると、人間でいう思春期が訪れ、大人への階段をのぼり始めます。
去勢手術、避妊手術をする前の猫は、外へ出たがる傾向にあるため、万が一に備えた脱走対策を講じておきましょう。
まとめ
1歳までの仔猫には、週齢に応じた食事やしつけがあります。
適切な時期のワクチン接種、去勢・避妊手術で、猫が健やかに暮らせるように配慮してあげましょう。
社会化期の過ごし方は、猫の成長へ大きな影響を与えます。
叱らずやさしく見守りながら、必要なお世話をしてあげてください。
- 猫と暮らす
- ピックアップ