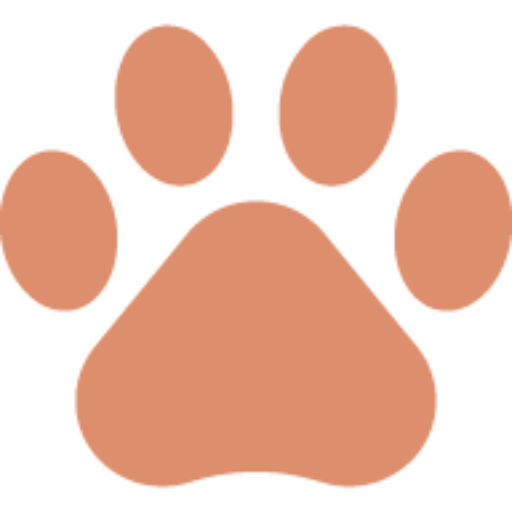- 猫の健康管理
2023.03.16
太りすぎは万病のもと

猫の肥満はさまざまな病気の原因になります。
飼い主がこまめにチェックして、適正体重を目指しましょう。
猫が太っているからといって、安易に食事を減らすのは危険です。
ダイエットする場合は、猫に合ったペースで進めてください。
太っているとどんなリスクがあるのか、猫に適したダイエット法を知って、毎日健康に過ごせるようにしましょう。
猫の肥満はどう判断する?
猫の肥満は、BCS(ボディコンディションスコア)で判断します。
年齢に応じた平均体重も参考になりますが、猫によって体格差があるため、BCSでの判断がおすすめです。
具体的には、猫のろっ骨をボディチェックして確かめます。
BCS1:やせすぎ
ろっ骨に脂肪がなく、すぐに触れられる。
横から見るとお腹が深くへこみ、上から見ると砂時計のように見える状態。
BCS2:やせ気味
ろっ骨が薄い脂肪に覆われていて、腰にくびれがある状態。
BCS3:理想体型
ろっ骨がわずかな脂肪に覆われ、お腹がなだらかに盛り上がっている。腰には適度にくびれがある状態。
BCS4:太り気味
ろっ骨が脂肪に覆われ、触るのが難しい。お腹は丸みをおび、腰のくびれがほとんどない状態。
BCS5:太りすぎ
ろっ骨が厚い脂肪に覆われていて、触るのは非常にむずかしい。
お腹も厚い脂肪に覆われ、くびれがみられない状態。
飼っている猫が太り気味、太り過ぎの傾向にある場合は、標準体型を目指して生活習慣を改善しましょう。ダイエットの進め方は、この後くわしく紹介いたします。
猫が肥満だとどんなリスクがあるの?

猫が肥満だと、糖尿病や高血圧、心臓や呼吸器の疾患、膀胱炎、尿石症などの病気になりやすくなります。
ジャンプする機会が多い猫は、体重増加による関節への負担も心配です。
ひどい場合は、椎間板ヘルニアや靱帯断裂を起こす恐れもあります。
ぽっちゃりした猫は愛らしいですが、長生きしてもらうためにも、飼い主が体重管理しましょう。
正しい猫ダイエットのはじめ方

猫のダイエットは、負担がかからないように少しずつ進めます。
数か月~1年など、長期的な計画を立ててください。
ダイエットの進め方は、
- 摂取カロリーを減らす
- 運動量を増やす
この2つが基本です。
肥満と判断できるBCSレベルでも、痩せるべき体重は数百グラム程度、という場合があります。極端に食事を減らし過ぎないように注意しましょう。
目安として、1週間に1%前後の減量を心がけてください。
適正なカロリー量や1日にどのくらいカロリーを減らすべきか、適正と思われる体重はどのくらいか、獣医に相談しながら進めると安心です。
ご飯の場所を分散して食べる量や運動量を増やす、空腹を感じにくいように小分けにするのも良い方法です。
留守中のフード調整が難しい場合は、自動給餌器で量をコントロールしましょう。
食事管理と同じくらい、運動習慣も大切です。
キャットタワーや猫が楽しく身体を動かせるおもちゃを用意して、スキンシップを楽しみながら、運動習慣をつけましょう。
ひとり遊びができるおもちゃがあると、より運動量を増やせます。
多頭飼いの場合はどうする?

猫を2匹以上飼っている場合、太り気味の猫が他の猫のごはんを食べてしまう恐れがあります。
ダイエット中の猫がいる場合は、食事の場所を分けて与えるようにしましょう。
他の猫が食べ残したフードは、速やかに片付けてください。
食事をケージで与える。
1匹ずつ順番に与える、というのも良い方法です。
順番にあげる場合は、先住猫を優先してください。
まとめ
病気を未然に防ぐなら、適正体重の維持が欠かせません。
BCSをチェックして、肥満の傾向がみられる場合は、ダイエットをスタートしましょう。
欲しがるだけ与えるのではなく、決まった量を守る生活習慣も大切です。
減量用のフードもありますので、獣医師と相談の上、活用してみてください。
- 猫の健康管理