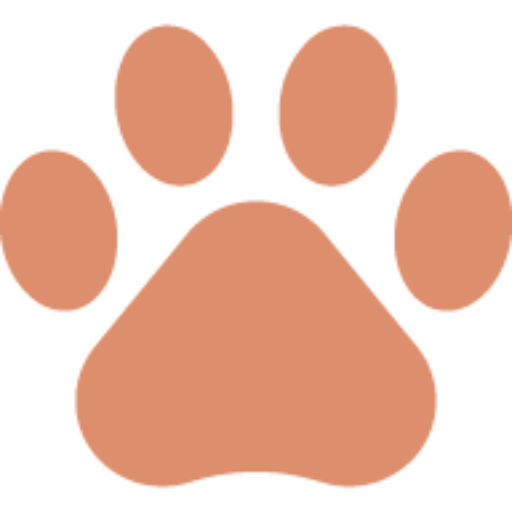- 猫を迎える前の心構え
2023.06.06
猫にとって安全な家?

現在、完全室内飼育で猫を飼う家庭が増えています。
外出は危険が多いため、猫を安全に飼うなら室内飼いがおすすめです。
その一方で、室内で飼っているからと油断し、トラブルが起きるケースもあります。
どんなに気を付けていても、100%安全な家にはなりません。
できる配慮はすべてするつもりで、猫にとって安全な環境を用意してあげましょう。
室内にはどんな危険がある?
獣医師のもとには、室内で起きたさまざまなトラブルを理由に、猫がやってきます。
どのような事例に注意するべきか、チェックしておきましょう。
フレグランス

普段から香水を身につけたり、アロマを焚いたりしていませんか?
人間は、香水やアロマに含まれる毒素を、肝臓で分解しています。。
ところが、猫の肝臓には、解毒に必要なグルクロン酸抱合能がなく、アロマオイルを無害化できません。少量でも中毒になりやすいことから、猫がいる部屋では極力アロマオイルを使用しない方が良い、といわれていますが、
尚、すべての香水、アロマに含まれる解毒機能がないと証明されているわけではありません。
フレグランスやアロマを嗅ぐと、猫に有害になるケースが多いと心得て、猫と暮らす室内では使用しないようにしましょう。
ハイター
除菌などに使われるハイターは、普段から家の消毒に使用している方が少なくありません。
ですが、人間にとっても危険のあるハイターは、猫にも影響を与えます。
ひどい場合は、嘔吐や肺炎を引き起こすケースがあります。厳重に保管し、猫のいる空間では使用しないようにしましょう。
観葉植物

室内環境に癒しを届ける観葉植物。
「自然を感じてほしい」
そんな理由で猫との空間に置いている飼い主さんもいると思います。
ですが、観葉植物や近年人気が高い多肉植物の多くが毒性を持っています。
また花屋などの並ぶ植物の種類が増え、どれが中毒を起こすのか、獣医師でも把握しきれないのが現状です。
猫が食べても大丈夫な猫草以外は、生け花や観葉植物であっても置かないようにしましょう。
ひも状のもの

紐がついたおもちゃで遊ぶのが大好きな猫。
家に合った紐を揺らして、猫と遊んでいませんか?
紐で遊ぶだけなら良いのですが、遊び終わったあとの紐を放置してしまった場合、猫が飲み込んでしまう場合があります。
ひも状異物を誤植してしまうと、腸閉塞などを引き起こす可能性があり大変危険です。
紐で遊んでいるうちに体に絡まり、首が締まってしまったという事例もあります。
紐だけでなく、ビニールテープ糸など、長細くて丸のみの危険があるものを、置きっぱなしにしないように注意しましょう。
ジョイントマット・コルクマット

猫の足音を減らしたい、寒さ対策をしたい、などの理由で、ジョイントマットを敷いている家庭が少なくありません。
このジョイントマットも、猫の誤飲につながります。
ジョイントマットやコルクマットのつなぎ目部分や端の部分を好み、食べてしまう猫が一定数います。
大量に食べてしまうと腸閉塞などの危険があるため、何かを敷く場合は猫がかじらない素材を選びましょう。
小物

人間の赤ちゃんと同じように、猫も気になったものを口に入れてしまう傾向があります。
特に仔猫は、何にでも興味を示すため、口に入ってしまうサイズの小物を置かないように気を付けましょう。
「誤飲・誤食が多い小物」
・ボタン
・画鋲
・消しゴム
・ティッシュ
・裁縫道具
・糸や毛糸
・輪ゴム
・ビニール製品
・洗剤
・ボタン電池
・硬貨
・タバコ
・薬
など、室内には危険がたくさんあります。
高いところに置いても取ってしまう猫が多いこと。
戸棚を開けてしまう猫が多いことから、猫用に扉をロックしておく必要もあります。
「誤飲したかもしれない」
「普段と違った様子がみられる」
という場合は、速やかに動物病院を受診してください。
まとめ
室内で飼っていても、猫にとって完全に安全な家、とはいえません。
できる対策は全部講じて、健やかに猫が育つ家を目指しましょう。
紹介した以外にも、人間の食事を食べてしまったり、猫用おやつをパッケージごとかじってしまったり、想像の上をいく思いがけないものに興味を示し、口にしてしまうケースがあります。
何に興味を示しているのか、日ごろからよく観察して、食べてしまいそうなものがあれば、早めに対策しておきましょう。
- 猫を迎える前の心構え