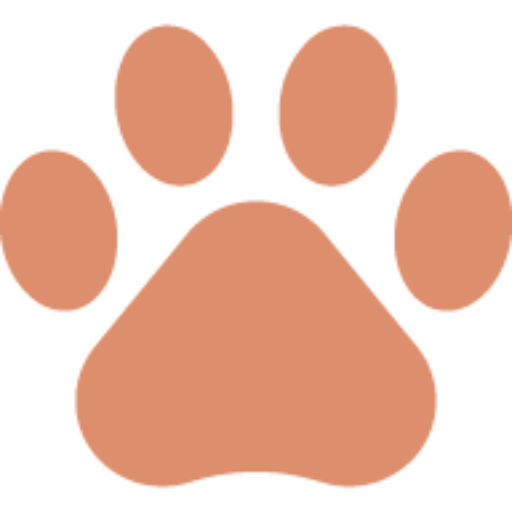- 猫と暮らす
2023.06.06
耳掃除やシャンプーは必要?

愛猫のお世話、どこまで自分でするべきか分からず、悩んでいる飼い主さんが少なくありません。
そこで今回は、
「シャンプーはするべき?」
「耳掃除はどうやってするの?」
「肛門絞りが必要って聞いたけれど本当?」
そんな飼い主さんの疑問にお答えいたします!
猫にシャンプーは必要?

ペットショップへ行くと、さまざまな猫用シャンプーが販売されています。
そのため、
「猫は定期的にシャワーをしたり、お風呂に入れたりするもの」
と思ってしまう飼い主さんも多いのですが、シャンプーやリンスは基本的に不要です。
猫はにおいが少なく、トイレ以外はそれほど臭いません。
また、日ごろからセルフグルーミングで身体を清潔に保っているため、ブラッシングのみのお手入れで十分なケースが多いでしょう。
長毛種の場合、皮膚までブラシが届かなかったり、毛が絡まってしまったり、猫が舐めただけでは汚れが落ちなかったり、という場合があります。
このように、汚れやにおいが気になる場合は、飼い主さんが定期的にシャンプーしてあげてください。
猫をシャンプーする手順
猫をシャンプーする場合の手順をみてみましょう。
①
シャンプー前にブラッシングをしたら、ぬるま湯を使って体を湿らせます。
シャワーを嫌がる場合は、洗面器でそっとお湯をかけてあげましょう。
②
しっかり泡立てたシャンプーを使って、皮膚を軽くマッサージするように洗ったら、顔からお尻へ毛の流れにそってすすぎます。シャンプーの成分が残らないように、入念に流しましょう。
③
次に、清潔なタオルでしっかり水分を拭きとってください。ドライヤーの時間を短縮するためにも、ていねいなタオルドライが重要です。
④
最後に、熱くないように猫からドライヤーを20cm程度遠ざけた状態で温風を当て、毛を乾燥させます。猫がドライヤーを嫌がる場合、自然乾燥だと身体が冷えてしまいます。必要がない場合は、無理にシャンプーしなくても大丈夫です。
ドライヤーを嫌がる猫をシャンプーしたい場合は、お世話に慣れている動物病院やトリミングサロンを利用しましょう。
飼い主さんがするべき猫の耳ケア

セルフグルーミングが得意な猫ですが、顔を洗う動作をしていても、耳の中まではきれいにできません。月に1~2回程度でかまいませんので、耳の中が汚れていないかチェックしておきましょう。
猫の耳掃除には、専用の耳洗浄液(イヤークリーナー)を使います。
洗浄液が含まれている、便利なウェットシートタイプも販売されています。
耳洗浄液がない場合は、ぬるま湯でも大丈夫です。
耳洗浄液を使用する際は、コットンに液を含ませて、見える部分だけやさしく拭きます。耳の奥まで拭いてしまうと、トラブルの原因になるため避けてください。
綿棒を使用する飼い主さんもいますが、乾いた綿棒を使ってしまうと、摩擦により炎症を起こす恐れがあります。
「コットンではどうしても落ちない」
という場合は、耳洗浄液を綿棒に含ませて、奥に入ってしまわないように丸い部分の根元を持って掃除しましょう。
黒い耳垢がたくさんある、猫が足で耳を何度もかいている、という場合は病気の可能性があります。外耳炎やミミダニ、マセラチア、細菌感染などが疑われるため、早めに動物病院を受診してください。
スコティッシュフォールドなど、折れ耳の猫は特に耳の汚れが溜まりやすいため、定期的にチェックしてあげましょう。
飼い主さんがするべきお尻のケア

お尻のケアが必要なのは犬だけ、そう思っていませんか?
トリミングサロンで犬の肛門絞りメニューがあるように、猫にもお尻のケアが必要です。
「猫のお尻がいつもより臭い」
「猫がお尻を引きずって歩いている」
「猫がお尻を気にして、ずっと舐めている」
という場合は、肛門腺液が溜まっている可能性があります。
猫の健康のためにも、臭い対策のためにも、数ヶ月に1度程度、肛門の右下と左下部分に手を添えて、ぎゅっと絞ってあげましょう。
肛門絞りはコツが必要なため、猫が嫌がる場合は獣医師に相談してください。
まとめ
比較的お手入れが少ない猫ですが、耳やお尻のケアをしてあげると、より快適に過ごせます。
必要なお世話アイテムを用意して、定期的にチェックしてあげましょう。
ケアを通じて、猫の様子をよく観察できるため、猫の異変に気付きやすい点もメリットです。
猫の性格、毛の長さ、状態に応じて、適切なケアをしてあげてください。
- 猫と暮らす