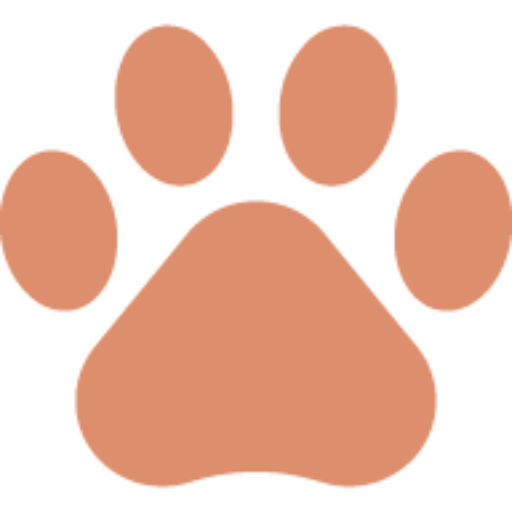- 猫の健康管理
2023.06.07
定期的な健康診断の勧め

猫と暮らしている飼い主さんの中には、
「病院は具合が悪い時しか行かない」
「ここ数年は一度も動物病院にかかっていない」
という方がいるかもしれません。
元気だから大丈夫、とつい考えてしまいがちですが、猫に多くみられる腎臓病や心臓病、がんなどが、みえないところで進行している可能性があります。
手遅れにならないためにも、定期的な健康診断で、猫の身体をチェックしておきましょう。
猫の健康診断はいつ行けばいい?
猫の健康診断は、成猫で年に1回、シニア期は年に2回受けておくと安心です。
15歳を過ぎてからは、年3回の検診が推奨されています。
検診へ通う頻度は、猫の種類、持病、健康状態などによっても変わります。
かかりつけ医に、どのタイミングがベストなのか相談してみましょう。
長毛な猫のブラッシング目的、予防薬の塗布ついでに毎月簡単なボディチェック、といった目的で動物病院にかかる飼い主さんもいます。
通院は猫によってはストレスになるため、その子のキャラクターに合わせたり、暑い季節、寒い季節は避け、過ごしやすい春や秋を選ぶと、負担を軽減できます。
検査にあたり、
「便を持参してください」
「自宅で採尿してきてください」
「前日9時以降は絶食で来院してください」
といった指示がありますので、先に電話などでたしかめておきましょう。
猫の健康診断では何をするの?

猫の健康診断は、簡単な診察から検査希望の場合は幅広い項目をチェックできます。
主な検査項目は以下の通りです。
・一般検診(体重測定・検温・視診・聴診・触診など)
・尿検査
・便検査
・血液検査
・超音波検査
・レントゲン検査
受ける検査の種類によって、費用が変わります。
金額や内容は、かかりつけ医で相談してください。
様子をみていて気になるところがある場合は、事前に獣医師へ相談しておくと、適した検査項目を追加してもらえます。
それでは次に、それぞれの検査内容をくわしくみてみましょう。
一般検診
目や耳、口の中の様子、においをチェックしながら、健康状態をたしかめます。
身体全体を手で触れて、皮膚の状態はどうか、お腹にしこりや腫れなどがないか、ていねいに観察の上、診察してもらえる先生をみつけましょう。
心音やお腹の音は、聴診器を使ってチェックします。
尿検査
自宅、もしくは動物病院で採取した尿を検査します。
持参する場合はなるべくきれいな状態で採取し、30分以内を目安に持参しましょう。性状による変化や、汚染による細菌増殖などの影響が出ないうちに、極力早めにもっていけるよう心がけてください。
PH値、ビリルビン、糖尿病、潜血、尿たんぱく、尿比重などの検査結果から、病気の恐れがないか診断してもらえます。
猫は腎臓病や膀胱炎、尿道炎、尿路結石、糖尿病、尿路異常など、泌尿器の病気が多くみられる動物です。定期的な尿検査で、早期発見に努めましょう。
便検査
便の硬さやにおい、色を直接確認した後、顕微鏡を使って細菌の様子や寄生虫がいないかどうかをたしかめます。健康診断のタイミングでなくても、便の様子がいつもと違う場合は、便検査しておくと安心です。
血液検査
血液検査では、貧血の有無や白血球、血小板数にトラブルがないか、腎臓や肝臓、すい臓、電解質、高脂血症がないかなどの他、ウイルス検査、ホルモン疾患、心臓病マーカーなど、さまざまな異常をチェックできます。どこまで検査したいか先生と相談してから行うと良いでしょう。
病院や検査内容によってその場で結果が分かるケースと、後日結果を聞きに行くケースがあります。
レントゲン検査
臓器や骨に異常がないかどうか、レントゲンを使ってチェックします。
仰向けと横向きの2枚を撮影し、診断するのが一般的です。
超音波検査
猫の臓器に異常が起きていないか、超音波でたしかめる検査です。
お腹の検査は通常は仰向けで行い、内臓の状態を確認します。
心臓(胸部)は心臓疾患や雑音の精査の為に必要に応じて行われます。
まとめ
猫と長く一緒に暮らすなら、定期的な健康診断が欠かせません。
1年ごと、半年ごとのデータが残っていれば、体調を崩したときに振り返ってチェックできる、というメリットもあります。
病院嫌いの猫を飼っている場合、腰が重くなってしまいがちですが、病気を早い段階で発見するために、適切な治療をするために、定期的な健診を心掛けてあげてください。
- 猫の健康管理