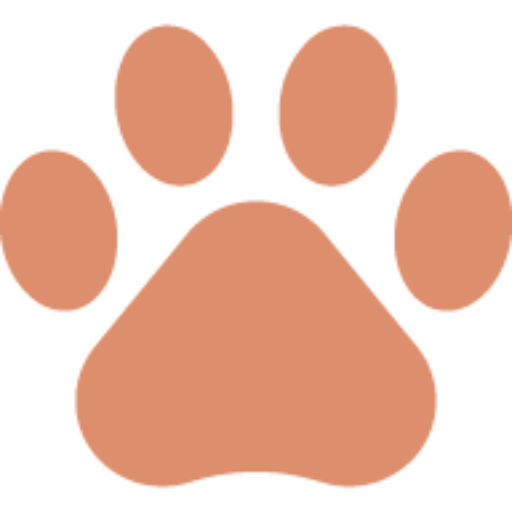- 猫の健康管理
2023.06.07
病気のサイン

この記事の目次
会話のできない猫ですが、体調が悪い時はなんらかのサインを出しています。
このサインに飼い主がいち早く気づき、病院を受診できると、症状が軽いうちに対処できます。
今回は、覚えておきたい猫が出す病気のサインについて、いくつか解説いたします。
猫が出す病気のサイン
猫に異変がある場合、身体のいたるところからサインが出ています。
毎日撫でたり、抱っこしたりしながら、病気のサインがないか、たしかめておきましょう。
いつもより元気がない
猫がいつもより元気がない場合、身体に痛みや不調を感じているかもしれません。
おもちゃで遊ばない、高いところに登りたがらないなど、元気がない場合は病気を疑ってみましょう。
食欲がない
普段は食べられる量を残してしまう、ごはんを催促しない、など、猫の食欲がない場合は、病気のサインです。
歯が痛くて食べられない、消化器に不調を抱えている、ストレスを感じているなど、さまざまな原因が考えられるため、早めの受診がおすすめです。
水をたくさん飲む、尿量が増えた、よく吐くという場合も病院へかかりましょう。
性格が変わった
猫が急に人を避けるようになった、良く鳴く(鳴かない)ようになった、落ち着きなくうろうろしている、すぐ怒るようになった、など、性格が変わったように感じる場合にも病気が隠されている恐れがあります。
気のせいかもしれない、と放置してしまうことなく、かかりつけ医に相談してください。
寝る時間が長くなった
猫は良く寝る生き物です。シニア期に入ると、さらに寝る時間が長くなります。
ですが、あまりにも寝過ぎている、じっとしていることが多くなった、という場合、動くのがつらいなどの原因があるかもしれません。
猫の様子を観察して、眠っている時間が長過ぎる場合は、病院で相談してみましょう。
尿や便の変化
泌尿器が弱い猫だからこそ、尿はかならず毎日チェックしてください。
尿の量が増えたり、減ったりしている、尿の色がいつもと違う、という場合はすぐ病院を受診しましょう。
白いペットシーツが使えるシステムトイレを選ぶと、毎日の量、色が確認しやすいためおすすめです。
尿だけでなく、下痢や軟便、便秘の場合も、続く場合は病気を疑ってみましょう。
体重の変化
猫が痩せてきた場合、病気が隠れているかもしれません。
加齢により筋肉量が低下して痩せたケースだけでなく、糖尿病の場合で急に痩せるケース。
徐々に痩せる慢性腎臓病や腫瘍疾患、しっかり食べているのにどんどん痩せてしまう甲状腺機能亢進症など、痩せ方によってさまざまな病気が疑われます。
逆にストレスなどが原因で食べ過ぎ、太ってしまう猫もいます。
定期的に猫の体重をチェックして、著しく増減がある場合は動物病院を受診しましょう。
目の変化
目が赤い、目をかゆがる、目やにや涙が出るなど、いつもと目の様子が違う場合、なんらかのトラブルが起きている可能性があります。
放置してしまうと、さらにひどくなるケースが多いため、早めに適切な処置、投薬をお願いしてください。
口の変化
口に病気が隠されている場合、猫の口がくさい、口周りを触ろうとすると嫌がる、よだれが出る、口の中の色が普段と違う、といった変化がみられます。
若いうちから歯みがき習慣をつけて、定期的に口の中の様子をチェックしましょう。
耳の変化
耳をかゆがる、耳が汚れている、耳からにおいがする、という場合、耳の病気の疑いがあります。通常猫の耳は、特にケアしなくても汚れたり、においがしたりしない部分です。
飼い猫の耳に変化をみつけたら、かかりつけ医で相談してください。
鼻の変化
くしゃみや咳をしていたり、鼻水が出ていたり、呼吸が苦しそうだったり、こんな様子をみかけたら、早めに病院を受診しましょう。
人にとってはただの風邪程度の症状でも、猫の場合はさまざまな疾患の可能性があります。
いち早く原因をみつけて、正しい治療を施してあげましょう。
身体の変化
皮膚をかゆがる、毛が抜ける、毛づくろいをしない、身体に腫れやしこりがある、触られるのを急に嫌がる、という場合は、病気が疑われます。
病気を早期発見するために、日ごろから身体をよくチェックしておきましょう。
まとめ
その他にも、歩き方がいつもと違う、鳴き方がおかしい、ぐるぐる回る、食べた後なのにまだ食べたがる、など飼い主だから気付ける変化があると思います。
ささいな変化であっても放置は厳禁、獣医師へ相談してください。
こまめな体調チェック、受診ができていれば、症状が小さいうちに対処できます。
猫の健康のために、身体の様子や行動を良くたしかめておきましょう。
- 猫の健康管理