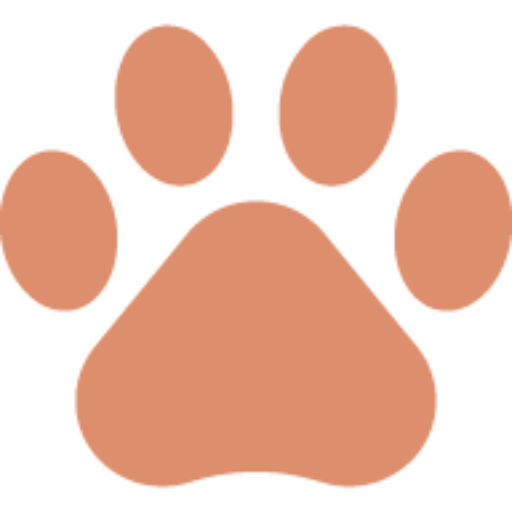- 猫と暮らす
2023.06.07
SFTS

「SFTS」という感染症を聞いたことがあるでしょうか?
人間にも猫にも感染する 人獣共通感染症の一つで、致死率が高いウイルスとして知られています。
西日本で特に多くみられ、猫も飼い主さんも対策が必要です。
SFTSを予防するために何をするべきなのか、チェックしておきましょう。
SFTSとは
SFTSは、ウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染する病気の一つです。
重篤熱性血小板減少症候群とも呼ばれ、日本国内でも多くの猫や犬、飼い主さんが発症しています。
その致死率は非常に高く、2022年7月31日の時点で763人の人が感染、91名が亡くなっています。※1
※1 国立感染症研究所/重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html
猫の場合は、致死率が60%を超えているという報告※2があり、日々の予防が欠かせません。
※2 日本ウイルス学会/ネコにおける重症熱性血小板減少症候群
http://jsv.umin.jp/journal/v69-2pdf/virus69-2_169-176.pdf
成虫が多い春、若ダニや幼ダニが多い秋は特に注意が必要な季節です。
マダニは全国でみられることから、まだSFTSの症例が出ていない地域であっても、きちんと対策しておきましょう。
マダニに咬まれるとどうなる?
SFTSを保有しているマダニに咬まれた場合、6日~2週間の潜伏期間を経て、症状が出ます。マダニに咬まれたと気づいたら、その日から2週間は慎重に健康状態をたしかめましょう。
SFTSに感染している場合、発熱や倦怠感、下痢、嘔吐、腹痛や食欲低下などの消化器症状、リンパの腫れ、筋肉痛、意識障害、出血、白血球や血小板の減少がみられます。
飼い猫にマダニがついている場合、あせってマダニを除去しようとしてしまいがちです。
ですが、マダニがつぶれてしまった場合、体液が飛び散る可能性があります。
櫛などでマダニを除去しても、頭部など一部が身体に残ってしまう恐れがあるため、自己処理ではなく動物病院で処置をお願いしましょう。
SFTSの予防法
SFTSを予防するためには、マダニのいそうな草むらや並木道などの場所に行かない、マダニを連れて帰らない、という配慮が欠かせません。猫は完全室内飼いを心がけ、飼い主さんが持ち帰ったマダニから感染しないように、通年を通したマダニ対策をしておきましょう。
ノミ取り首輪やノミ取りシャンプーなどが市販されていますが、首輪型は首の周りにしか効果がないこと、猫をこまめにノミ取りシャンプーで洗うのは難しいことから、動物病院で処方されるスポットタイプの薬を使うのがおすすめです。
室内で飼っていても、ベランダに出てしまった、脱走してしまった、というタイミングでマダニに咬まれる可能性もあります。定期的なケアで、猫をSFTSから守ってあげましょう。
人の場合は、マダニに咬まれないように、肌の露出を避けましょう。
マダニの多い自然豊かな場所を散歩する、仕事で山へ行く機会が多い、という場合は、長そで長ズボン、首にタオル、帽子などで身体を守り、服の袖や裾は手袋やズボン、長靴に入れておくと安全性が高まります。
外から帰ったら、マダニがついていないか、マダニに咬まれていないかチェックしてから部屋に入りましょう。
SFTSの治療法
SFTSには、まだ有効な治療法が確立されていません。
ワクチンもないことから、症状に応じた治療で様子をみるしかありません。
命に別条がない場合も、重篤な症状を引き起こす例が多く、入院治療になるケースが少なくありません。
飼い主さんが入院してしまった場合、猫に大きなストレスがかかりますし、猫が入院してしまった場合も普段とは違う環境、SFTSの症状でつらい時間が待っています。
猫も人も元気に暮らすために、徹底したマダニ対策をしてください。
まとめ
SFTSの症例は、毎年一定数確認されています。
西日本の郊外が主な感染場所ですが、いつ広まるかわからないのが現状です。
マダニは咬まれても自覚症状が少なく、気が付いたら深刻な状態になっているケースが少なくありません。
猫のためにも、自分のためにもできるマダニ対策を万全にして、感染を予防しましょう。
- 猫と暮らす