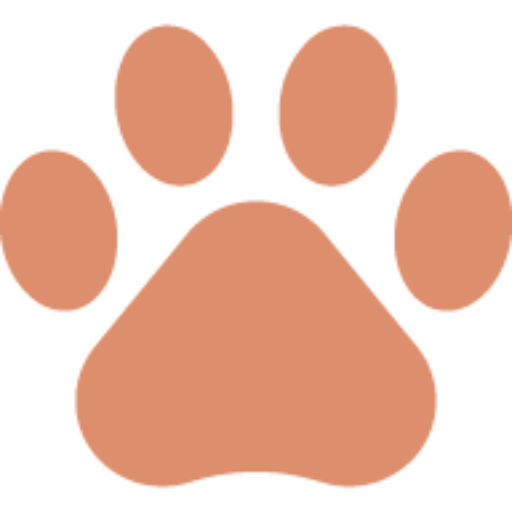- 高齢猫と暮らす
2023.06.09
がん

日本人の死因1位として知られる「がん」
人だけでなく、猫もがんにかかってしまう場合があります。
猫のがんとはどのような病気なのか。
発症する原因や付き合い方について、解説いたします。
猫のがんってどんな病気?
猫のがんも人と同じく、がん細胞の増殖によって発症します。
通常は免疫の力で排除できるのですが、免疫力が落ちていると、がん細胞の排除がうまくいかず、悪い細胞が増え続けることになります。
腫瘍ができても良性の場合は成長が遅く、転移しません。
良性腫瘍で害を及ぼさない場合は、様子をみて、腫瘍が増大する場合は切除を検討します。
悪性腫瘍の場合はどんどん進行してしまいます。全身に広がってしまう例もあるため、早めの対策が必要です。
どのような治療法が考えられるのか、動物病院で説明を受けましょう。
猫のがんを予防する方法
猫のがんは、年齢が主な原因です。
そのためシニア期に入ったら、普段以上に注意して様子をみる必要があります。
そのほかにもストレスや肥満、慢性炎症、感染症が原因で、がんになるケースが考えられるでしょう。
がんに関連している感染症は、以下の2つです。
・猫白血病ウイルス感染症
・猫免疫不全ウイルス感染症
外の猫から感染する恐れがあるため、猫はかならず室内で飼いましょう。
外に出している場合、万が一脱走した場合を考えるなら、猫白血病ウイルス感染症のワクチンを打っておくのも一つの手段です。
白血病やエイズなどのワクチンは、1万頭から10万頭に一頭くらいの割合ですが、注射接種部位肉腫という悪性腫瘍ができるケースが報告されている点も、合わせて覚えておきましょう。
メスの場合は、発情期前に避妊手術を受けることで、乳腺腫瘍の予防になります。
人と同じく、タバコの煙はがんの原因になるため、猫を飼っている部屋で喫煙しないように注意してください。
できるだけ早くがんに気づくため、定期検診も欠かせません。
がんを早く発見するために、血液検査と合わせてレントゲン検査や超音波検査も受けておくと、早期発見につながります。
猫ががんになってしまった時の症状

猫のがんは、腫瘍ができる位置によっては、早期発見が可能です。
全身をなでながら、しこりや腫れができていないか、たしかめてみましょう。
その他にも、
・咳がでる
・鼻水やくしゃみ、鼻血がみられる
・元気がなくなる
・よく吐く
・尿量が減る、増える、血尿がみられる
・下痢や便秘になる
・食べる量が減る(痩せる)
・治らない傷がある
・猫の性格が変わる
このような症状がみられる場合があります。
腫瘍が内臓にできている場合、よく触れあっていても、しこりや腫れに気づけません。
シニア期に入ったら猫をよく観察して、普段の様子にがんの兆候が出てないか、チェックしておきましょう。
猫のがんはどう治療する?
猫ががんになってしまったら、
・外科療法
・放射線療法
・化学療法
・免疫療法
といった治療の選択肢があります。
猫の年齢やがんの種類、腫瘍がある部位や大きさなどによって、適した治療があります。
かかりつけの獣医師と、治療方針をよく相談しましょう。
場合によっては手術や治療ができないケースもあります。
この場合は、がんの痛みを少しでも減らしてあげるため、緩和ケアを取り入れましょう。
・痛み止めの薬を飲む
・注射や点滴を打つ
・痛い部分を温める
・寝心地の良いベッドに変える
といった方法で痛みを軽減できます。
まとめ
猫ががんになってしまったら、まずは治療方針を決めるところからはじめます。
診断結果、治療方針に納得できない場合、がんに強い専門の動物病院で治療を受けたい場合は、セカンドオピニオンを検討しましょう。
手術や治療のリスク、痛みの有無、費用などを検討の上、最善だと思われる治療法、過ごし方を選択してください。
- 高齢猫と暮らす