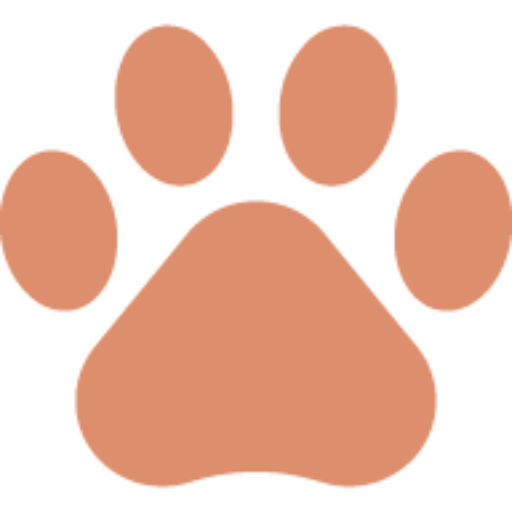- 高齢猫と暮らす
2023.06.09
心筋症、大動脈血栓塞栓症

猫の病気にはさまざまな種類があります。
その中でも怖い病気とされているのが「心筋症」と心筋症が原因で起きる「大動脈血栓塞栓症」です。
どのような病気なのか、発症してしまった場合に飼い主ができることはあるのか、治療や対処法を知っておきましょう。
猫の心筋症
猫の心筋症とは、その名の通り心臓に障害を起こす病気です。
心筋症と一言でまとめてしまいがちですが、
・肥大型心筋症
・拡張型心筋症
・拘束型心筋症
といった種類があります。
主にこの3例ですが、不整脈源(原)性右室心筋症、未分類の心筋症を発症する場合もあります。
心筋症の症状
猫が心筋症にかかると、
・元気がなくなる
・呼吸数が増える
・口を開けて呼吸する
・呼吸が苦しそうになる
といった症状があらわれます。
初期の段階では、少し元気がないようにみえる、食欲が落ちた、といった年齢に伴う変化に近い症状しか出ないため、見過ごしてしまいがちです。
症状が出てしまっている場合、余命宣告を受けるケースが少なくありません。
できるだけ長生きしてもらうために、定期的に動物病院を受診する。
気になる部分があれば、早めに受診の上、元気そうに見えてもレントゲン検査を受けたり、血液検査や心臓病マーカーを調べてもらい、異常があれば適切な投薬や治療を受けましょう。
心筋症は予防できる?
猫が心筋症を発症するメカニズムは、ほとんどがまだ解明されていません。
かかりやすい猫種とそうではない猫種がいるため、遺伝子が要因という説がありますが、くわしい部分はこれからです。
拡張型心筋症については、タウリン欠乏が問題とされています。このことから、最近のキャットフードにはタウリンが含まれており、発症の報告はほとんどみられません。
一方で、タウリンを与えていても、拡張型心筋症を発症するケースがあるなど、早期の原因解明が求められています。
このように、心筋症はまだ予防ができない病気です。
だからこそ、飼い主さんがしっかり様子をチェックして、普段と違うところがあれば、早期に獣医師へ相談しましょう。
猫の大動脈血栓塞栓症
猫が心筋症になると、左房に血栓症のもととなる塊ができます。その塊が腹大動脈の分かれ道のところで詰まってしまうため、左心房内に血栓ができやすくなります。
さらに左心室に流れ、大動脈から先へ流れ出ててしまうと、多くの症例で腹大動脈の分岐部で詰まってしまうため、後ろ足に症状が出ます。(突如叫んだと思ったら後ろ足の麻痺が起き、一気に全身状態が悪化してしまい、あわてて連れてこられることが多い。)
突然強い痛みに襲われるだけでなく、突然死してしまう可能性もあるなど、非常に怖い病気です。
心筋症が分かっていれば、大動脈血栓塞栓症を引き起こさないように、血栓形成を抑える薬を処方できます。
一方で、突然大動脈血栓塞栓症になるケースもあり、この場合は点滴や注射、外科手術、内科治療が必要です。
外科手術をしても、血流が改善できず足が壊死してしまうケースがあること、再発率が高いことでも知られています。どのような治療をしていくのか、獣医師とよく相談の上、決定してください。
大動脈血栓塞栓症の症状
大動脈血栓塞栓症にかかると、このような症状がみられます。
・身体を動かさない
・足を引きずる
・足が動かなくなる
・足が冷えている
・肉球が白もしくは赤紫色になっている
・足を触ると硬い
・足が硬直している
・足を触ると痛がる
・痛みで鳴く
・よだれが出る
心筋症を発症しているケースが多いことから、呼吸が苦しそうな様子がみられる場合もあります。
心筋症と同じく、動脈血栓塞栓症も予防法がない病気です。
異変に気づいたら、猫の命を救うために、救急で動物病院を受診しましょう。
まとめ
猫の病気はたくさんありますが、心筋症や動脈血栓塞栓症は非常に怖い病気です。
予防が難しい病気でもあるため、突然死を防ぐためにも、毎日の健康チェックや定期健診を欠かさないようにしましょう。
心筋症や大動脈血栓塞栓症の恐れがある場合、できるだけ早期に治療を開始する必要があります。
しばらく様子をみる、といった対応は控えて、すぐにかかりつけ医を受診してください。
かかりつけ医が診療時間外の場合は、夜間病院を利用しましょう。
- 高齢猫と暮らす