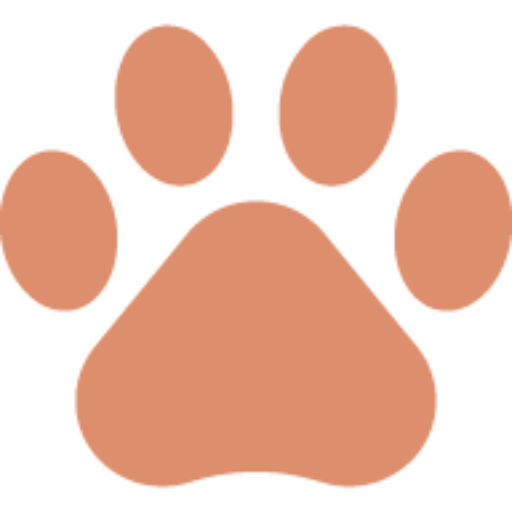- 高齢猫と暮らす
2023.06.09
認知症

人と同じく、猫も高齢になると認知症になる場合があります。
また人の認知症と同じく、次第に症状が進行していくため、初期の段階では気づかないケースがほとんどです。
長生きする猫が増えていることもあり、認知症との上手な付き合い方が求められます。
どんな症状がでるのか、どう対処したら良いのか、その時のために知っておきましょう。
猫の認知症はこんな症状が出る
猫が認知症になると、このような様子がみられます。
・ごはんを食べた後、また食べようとする
・ごはんの好みが変わる
・トイレを失敗してしまう
・夜中に大きな声で泣く
・攻撃的になる、もしくは普段以上に甘える
・名前を呼んでも反応がない
・おもちゃで遊ばない
・家の中で迷子になる
・同じところを徘徊している
・つまずいたり、ぶつかったりする
・音や変化に敏感になる
・元気がなくなる、もしくは活発になる
・不眠や過眠
・昼夜が逆転する
・身体を舐め続ける、噛み続ける
人の認知症と同じで、出る症状は猫によって違います。
複数の症状が一度に出る場合もあれば、年齢のせいで元気がないと思っていたら、実は認知症だった、というケースもあるでしょう。
またこれらの症状の多くが、腎臓病や関節炎、甲状腺機能亢進症など、猫に多い病気でもみられます。
認知症かもしれないと気づいたら、まずは動物病院を受診して、様子が違っている原因を探ってみましょう
猫が認知症になった場合の対処法
動物病院を受診しても、認知症を見極める検査法はありません。
そのため、血液検査やレントゲン、CT、超音波検査などで他の異常が見つからない場合、消去法で認知症と判断されるケースが一般的です。
認知症でトイレを失敗してしまう場合は、トイレを複数置いておく、入りやすい高さのトイレにする、トイレのカバーや扉を外す、といった方法で、間に合うようにしてあげましょう。
夜中ずっと鳴いている、と言うケースは、近隣の迷惑になったり、飼い主さんが眠れなかったり、というトラブルにつながります。鳴き続けて困っている場合は、鎮静剤などを処方してもらえますので、動物病院で相談してみてください。
その他に、認知症改善を目的にしたサプリメントも販売されていますので、獣医師と相談の上、試してみるのも良い方法です。
徘徊したり、ぶつかったりする場合は、危ない部分にクッションをつけておく、床に物を置かないようにする、歩いている範囲をサークルで囲む、といった配慮をしておきましょう。
普段以上に音や変化を気にする、触れられるのを怖がる、と言う場合は、やさしく声をかけながら対応してください。驚かせないように、部屋のインテリアなどを突然変えるのは避けましょう。
猫の認知症については“猫も認知症になる”という事実が明らかになっているだけで、これといった決め手の治療法はまだありません。
ですが、認知症になっても、安心して暮らせる家、心をゆるせる飼い主さん、撫でてくれる手、おいしいごはんがあれば、幸せに暮らしていけます。
トイレや歩行など、できるサポートを取り入れて、認知症になってしまった猫が幸せに暮らせる環境を整えてあげましょう。
まとめ
猫が認知症になってしまったら、行動をよく観察して、暮らしやすい家づくり、介護体制が必要です。
認知症ではなく、病気が隠されている可能性があるため、検査や定期検診は欠かさないようにしましょう。
認知症になっても、グルーミングやトイレ、食事ができる猫ちゃんも多くいます。
できないことを一つずつサポートしながら、ひなたぼっこができる場所を作る、認知症でも興味を持てるおもちゃを探してみる、食事を小分けにする、といった配慮で、穏やかな老後を送れるようにしましょう。
- 高齢猫と暮らす