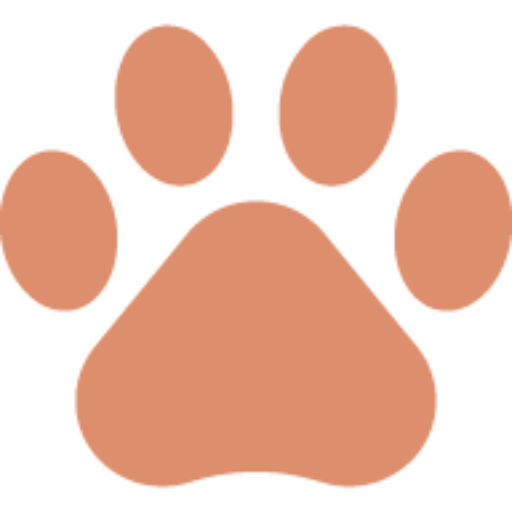- 猫とのお別れ
2023.06.12
Grief(死別の悲しみ)の心理過程

この記事の目次
大切に飼っていた猫が亡くなってしまったら、Grief(グリーフ)と呼ばれる死別の悲しみに襲われます。
突然の別れになるケースも多く、残された家族はGriefと向き合い、立ち直らなければいけません。
ペットに死が訪れた時、どのように気持ちが変化していくのか、心理過程を知っておきましょう。
Griefで起きる心理過程
大切な人やペットを失ったとき、どのような心理プロセスを辿るのでしょうか?
死生学を日本に広めた「アルフォンス・デーケン氏」が提唱している悲観12のプロセスから、立ち直りまでの過程をみてみましょう。
1.精神的打撃と麻痺状態
ペットの死は、覚悟していたとしても大きなショックを与えます。
精神的な打撃を受けるとともに、自分の心身を守るため、心や身体が麻痺状態になります。
2.否認
ペットの死という現実を受け止められず、何かの間違いではないか、息を吹き返すのではないか、悪い夢を見ているのではないか、という否認の心理状態になります。
3.パニック
死を否定しても変わらない現状を前に、パニック状態になります。
ペットをもう抱っこできない、一緒に過ごせない、という現実が押し寄せ、日ごろは穏やかな人であっても別人のように取り乱したり、乱暴になったりするケースがあるでしょう。
4.怒りと不当感
パニック状態が落ち着くと、怒りや不当感が表れます。
もっとできる治療はなかったのか、どうして世の中は病気のことをもっと広めないのか、といった他人への怒りや不当惑だけでなく、自分自身へ矛先が向く場合もあります。
5.敵意と恨み
怒りを通り越すと、敵意や恨みが芽生えます。
過失がないと分かっていても、猫と出会ったペットショップやブリーダー、治療にあたった獣医師などを恨むことで、ショックを和らげようとします。
6.罪意識
なぜもっと早く異変や病気に気づけなかったのか。小さな頃からもっと気をつけていれば良かった、など、自分への罪悪感でいっぱいになります。心の病気につながる可能性もあるため、メンタルケアが必要です。
現在進行形でペットを飼っている場合は、いざというときに後悔しないように、できることはすべてしておきましょう。
7.空想形成・幻想
空想形成・幻想は、現実逃避のような状態です。
猫が死んでしまった事実を受け入れられず、猫のごはんを用意したり、猫のお水を替えたり、といった行動がみられます。
家族がこのような状態になっている場合、無理に現実を突きつけるのは避け、時間が解決してくれるのを待ちましょう。
8.孤独感と抑うつ
猫の葬儀が終わる、月命日が訪れるなど、時間とともに気持ちが落ち着きます。
その一方で、猫のいない空間に寂しさや孤独を感じ、泣いたり落ち込んだりといった、元気のない状態になる場合があります。一人暮らしの場合は、特に抑うつ感が出やすいため注意しましょう。
9.精神的混乱とアパシー
孤独や抑うつ状態が続くと、アパシーと呼ばれる無気力状態になります。
猫のいない生活に幸せを感じられず、仕事や家庭、日常生活に影響を及ぼす場合があります。
10.あきらめ→受容
死という現実が変わらないことをあきらめ、受け止められるように気持ちが変化します。
そろそろ気持ちを切り替えなければと、自分自身で思えるようになる時期です。
11.新しい希望(ユーモアと笑いの再発見)
猫の死はつらいことですが、未来へ歩んでいくために、新しい希望を見いだします。
猫のことを思い出して悲しむだけでなく、幸せだった日を思い出して笑ったり、ユーモアを交えながら話せるようになったり、といった変化が訪れます。
12.立ち直りの段階(新しいアイデンティティの創造)
さまざまな過程を乗り越えて、立ち直りの時期がやってきます。
どれだけ悲しみにくれていても、いつかは新しいスタートが待っていると信じて、無理のない範囲で死を受け入れましょう。
まとめ
悲観12のプロセスは、かならずすべてが起きるわけではありません。
またいくつかのプロセスを行ったり来たりしながら、立ち直るケースもあります。
どの変化も、自分に起きる可能性があると心得ておきましょう。
ペットロスが長引かない方法については、別の記事で解説しています。
合わせてチェックして、愛猫との死をどう受け止めるか、考えてみてください。
猫とのお別れ:ペットロスが長引かないようにへリンク
- 猫とのお別れ