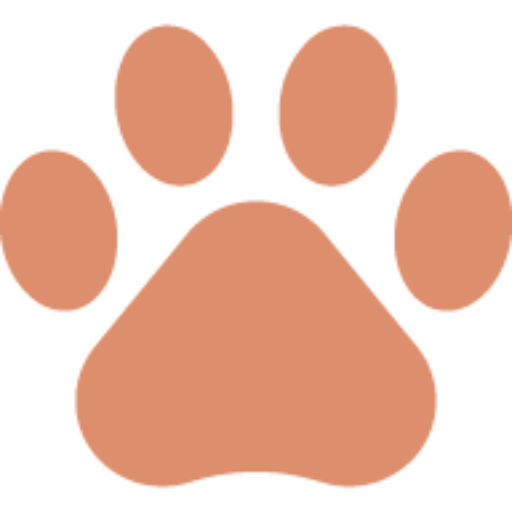- 猫を迎える
2023.03.09
猫の入手先

猫を迎えるには、いくつかの方法があります。
飼い主さんに適した迎え先を選んで、猫との生活をスタートしましょう。
今現在、殺処分されている猫の6割以上が仔猫、というデータ※があります。
※環境省/統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
飼いたい猫の種類が決まっていない場合は、里親募集している猫を選ぶと、小さな命を救えます。
猫を迎えるなら、事前に健康状態をチェックしておくと安心です。
この記事では、猫の主な迎え先と、獣医師監修の健康チェックリストを紹介いたします。
猫と幸せに暮らすために、事前に様子をたしかめてから、お迎えしてください。
猫を迎える4つの方法を紹介
猫の迎え先として、主に次の4つの方法が挙げられます。
それぞれのメリットや注意点をチェックしておきましょう。
ペットショップ

いろいろな猫の種類を比較したい場合、飼いたい猫の品種が決まっている場合は、ペットショップが身近です。
チェーン店の場合、ペットショップ内にいる猫だけでなく、遠くの店舗にいる猫を迎えられるシステムもあります。
店員さんに猫の性格や特徴を尋ねられる、猫を飼うのに必要なアイテムを一緒に揃えられる点がメリットです。
ペットショップによって、販売されている猫の種類、飼育環境はさまざまです。
いくつかのお店を回って、安心して購入できる店舗、一緒に暮らしたい猫を探してみてください。
ペットショップのホームページやSNSに、販売されている猫を掲載しているショップが多くあります。
飼いたい品種の猫、好みのカラーや顔の猫がいるかどうか、事前にチェックしておきましょう。
ブリーダー

ブリーダーは、純血種の猫を繁殖する専門家です。
飼いたい猫の種類が決まっている、母猫や父猫に会いたい、どのような環境で育てられたのか確認したい、という場合はブリーダーから迎える方法があります。
同じ母猫から生まれた兄弟をお迎えしたい、いずれは妹や弟の迎え入れたい、という場合も、ブリーダーが選択肢の一つになるでしょう。
全国にブリーダーがいますが、繁殖方法や飼育環境はさまざまです。
一緒に過ごしている他の猫や、飼育環境をみせてくれるブリーダーかどうか、たしかめておきましょう。
保健所や保護団体

事情で捨てられてしまったり、野良猫が生んだ猫が保護されたり、保健所や保護団体には不幸な猫がたくさんいます。
猫の命を救いたい場合、雑種の猫を迎えたい場合は、保健所や動物愛護センター、地域の保護団体などに足を運んでみましょう。
保健所や保護団体が開催している里親募集の譲渡会に参加して、様子をみてみるのも良い方法です。
各自治体の役所などにある掲示板、新聞、コンビニや動物病院の張り紙などから、保護猫情報を得られる場合もあります。
友人・知人

友人や近所に住む人から、猫を貰ってほしいと言われるケースがあります。
不幸な猫にしてしまわないためにも、条件が合うようならお迎えを検討してみましょう。
どこで生まれたのか、どのような経緯で保護したのかなど、できるだけくわしく聞いておくと、動物病院へかかる際に役立ちます。
野良猫を拾う

ふとしたきっかけで野良猫を拾うケースがあります。
里親を探すつもりで保護したけれど、愛着が湧いてそのまま飼うことになった、というケースが多くみられます。
野良出身の場合、ノミやしらみ、寄生虫、猫風邪など、病気を抱えている場合が少なくありません。
まずは動物病院で診察を受け、治療が必要な場合は処置からスタートしましょう。
元気な猫を迎えるチェックリスト

ペットショップやブリーダー経由で猫をお迎えする場合も、保護猫を譲り受ける場合も、事前に健康状態のチェックが欠かせません。
自分の手で抱っこして、元気かどうかたしかめておきましょう。
【猫の健康状態チェックリスト】
- 目のチェック
☑目ヤニがついていない
☑目が充血していない
☑目の色が白濁していない
- 耳のチェック
☑嫌なにおいがしない
☑耳アカがない
☑耳に触れると足で耳をかこうとする
- 口のチェック
☑歯茎が赤くない
☑よだれが出ていない
☑舌に潰瘍などがみられない
- 鼻のチェック
☑鼻の頭が湿っている
☑鼻水が出ていない
☑くしゃみをしていない
- 毛のチェック
☑フケがなく毛ヅヤが良い
☑皮膚のただれや脱毛がない
☑皮膚をかゆがる様子がない
- おしりのチェック
☑肛門の周りがきれい
☑肛門が締まっている
☑肛門周辺にただれがない
- しぐさのチェック
☑呼吸が規則正しい
☑足を引きずっていない
☑元気によく遊んでいる
当てはまるチェック項目が多ければ多いほど、健康状態が良い猫といえます。
中には、
「トラブルが起きている猫を保護してあげたい」
という場合もあると思います。
この場合は、できるだけ早く獣医師の診断を受けて、適切な処置をお願いしましょう。
- 猫を迎える